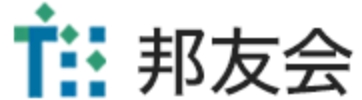ニュース
退職のご挨拶
「サービス・ラーニング」を見つめ直す
教育学部 今津孝次郎
2013年度から7年間の勤務で私なりに貢献できたと言えるのは、「教育学部」の完成と「教職支援センター」の立ち上げです。そして思いがけない成果となったのは「サービス・ラーニング」の取り組みでした。近隣の小学校が5月に開く運動会に入学直後の1年生が出かけてお手伝いしたことが好評だったことから、名東区内を中心にして幼稚園や保育園、児童館、図書館、名東文化小劇場など、活動の場が毎年のように広がっていきました。教育学部としては、単なる「ボランティア」ではなく「プレ教育・保育実習」としての「ラーニング」として捉えましたので、2年間の試行を経て3年目から授業化されました。

授業化された4年間を振り返ってみると、確かに授業形態としてすっかり定着するとともに、地域からもその活動が認められ、教育学部学生たちに手伝って欲しいとさまざまな依頼が舞い込むことになりました。今や地域に育てられる「サービス・ラーニング」に大きく成長し、地域連携の重要な機能をも果たしていると言えます。
ただその一方では、次の段階へと高め深めるべき時期に来ているように感じられます。単に、学校園などの現場を体験した、子どもたちと実際に触れ合った、先生方の動きをつぶさに見聞きできた、というだけではなくて、そうした諸経験を通してどのような「ラーニング」を実現できたか、が深く問われているということです。つまり、①諸活動を通して抱くさまざまな興味関心を大事にしてその後も探究し続ける態度を育てること、②多様な人々との出会いから対人関係を学ぶこと、③自分の感じ方や考え方を周囲の人々に理解してもらえるように率直に自己表現する力を養うこと、④何か失敗をしても乗り越える挑戦力や忍耐力を身につけること、⑤社会で守るべきルールを体得すること、など。
こうした五つの力や態度は一般に「非認知能力」と呼ばれ、これまで私たちが「知力」と馴染んできた「認知能力」とは違う要素で見落としがちであったことが、いま世界的に論議され始めています。つまり、「サービス・ラーニング」はこの「非認知能力」を育てる重要な活動として見つめ直す必要があるのではないか、という大きな課題です。言い換えると、教職や保育職に不可欠な「非認知能力」にもっと注目することにほかなりません。